債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。

札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
|---|---|
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。

札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
|---|---|
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 個人再生とは > 個人再生できないケースについて
更新日:2024/06/20

個人再生は、裁判所に申し立てを行い認められて初めて成立する方法です。
裁判所に認めてもらえなければ「個人再生ができない」ということになります。
それでは、裁判所は申立者の何を見て判断しているのでしょうか。
自分でも個人再生できるのかな?と疑問に感じている方のために、 個人再生できない場合について詳しく解説していきます。
目次
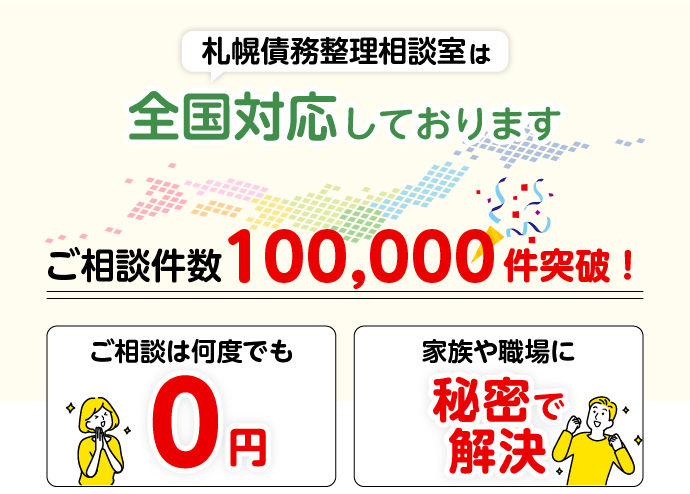
個人再生とは、裁判に申し立てをして、借金の総額を約5分の1程度にまで減額してもらった上で、残りの借金を原則3年(場合によっては5年に延期可能)かけて、債権者に支払っていくというものです。
個人再生は、自己破産のように借金がゼロになる訳ではありませんが、住宅を守りながら借金が大幅に減額されますので、住宅ローンがある方に多く利用されています。
ただし、この効果が絶大な個人再生ですが、手続きをおこなうためにはいくつか条件があります。
個人再生では、減額された額を計画通りに返済していく能力がなければ裁判所に認められません。
返済能力の基準は、減額された額を3年もしくは5年で分割払いしていけること。
例えば、1200万円の借金が最低弁済額の240万円まで減額できたとしましょう。
すると、個人再生では原則3年の分割払いなので、
240万円÷36か月≒約6万7千円
毎月、約6万7千円を3年間返済し続けられる能力があるのかどうかを、現状のあなたの経済状況をもとに判断されることとなります。
5年払いまで延長できた場合は、
240万円÷60ヵ月=4万円
毎月4万円を5年間継続して返済していける見込みがあるかどうかを裁判所に見られるわけです。
つまり、
・継続した収入
・返済計画を実行していける能力
これら2点が条件となります。
履行トレーニングでテストされる
返済計画を実行していける能力には、経済的能力はもちろん必要ですが、毎月の返済期日に遅れずにしっかりと返済していくことも求められます。
個人再生では、申し立てを行ってから認可されるまでの間を利用して、履行トレーニング(個人再生後と同様の毎月の返済額をテストという意味合いで振り込み)を行います。
この履行トレーニングで不備があった場合は、個人再生が認められなくなる可能性がでてきます。
個人再生には、最低弁済額基準というものがあります。
これは、借金額額ごとに決められており、以下の表のとおりとなっております。
| 借金額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 減額無し |
| 100万円~500万円未満 | 100万円まで減額 |
| 500万円~1500万円未満 | 借金額の1/5まで減額 |
| 1500万円~3000万円未満 | 300万円まで減額 |
| 3000万円~5000万円未満 | 借金額の1/10まで減額 |
| 5000万円以上 | 対象外 |
個人再生では、借金が100万円~5000万円の間に入っている場合に限り減額対象となりますので、100万円未満・5000万円以上の借金は個人再生ができないことになっています。
個人再生では、 清算価値保障の原則 というルールに従わなければいけません。
これは、保有している財産の額よりも減額できないというものです。
もし500万円の価値のある不動産をもっているとしましょう。
借金が400万円であれば、個人再生により100万円にまで減額できる可能性があるのですが、500万円分の財産を保有しているので500万円以下に減額することができません。
つまり、 借金額を超える財産を持っている場合は、個人再生では減額ができず、手続きをする意味が無いのです。
清算価値を下げるために、財産を隠そうと考えている方がいたら絶対にしないでください。
財産隠しで考えられるのは、不動産や車などの名義を別の人(家族や知人など)に変えておくなど、資産を移転することです。
財産隠しが発覚すると、再生開始決定の取消事由となったり、再生計画の認可決定が取り消される可能性があり、悪質な場合には、詐欺再生罪として刑事責任を問われる可能性があります。
個人再生は、一般的に司法書士に依頼し、裁判所に申し立てて進めていきますので、司法書士費用や裁判所費用が発生します。
司法書士費用は約30万円程度、裁判所費用が約20万円程度かかりますので、その費用を用意できないと個人再生を進めることができないのです。
ただし、司法書士費用も裁判所費用も基本的には分割払いなので、一度に全額用意する必要はないでしょう。
個人再生を利用する最大のメリットと言っても過言ではない、 住宅資金特別条項(住宅ローン特則) 。
住宅資金特別条項があるからこそ個人再生をする方も少なくありません。
住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンだけを個人再生の対象から外すことができますので、住宅を守りながら他の借金を減額することを可能にします。
しかし、この住宅資金特別条項を利用するためには条件があり、それは住宅ローンに他の担保権が設定されていないことです。
一般的に、住宅ローンの担保は住宅そのものに設定されていることが多く、今まで特に何もしてこなければ担保は住宅だけでしょう。
ですが、不動産担保ローンなどのように、住宅を担保に何か別のローンを組んでいたり、借金をしている場合は、「他の担保権が設定されている」状態となります。
このような状態になっていると、住宅資金特別条項を利用することができないため、住宅を守りながら借金の減額ができなくなってしまいます。
つまり、個人再生のメリットである住宅資金特別条項が利用できないことから、自己破産に切り替えた方がメリットが大きくなる可能性が高いです。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2パターンがあり、いずれかを選択します。
一般的に、借金減額効果が高いとされている小規模個人再生を選択するのですが、この小規模個人再生には、債権者に不同意(個人再生を認めない)を主張する権利があるのです。
それでは、1つの債権者でも個人再生に反対をすると個人再生ができなくなるのかというとそういうわけでもありません。
これには決まりがあり、
・債権者数の半数以上が反対
・借金額の1/2を超える債権者の反対
これら2ついずれかに該当すると小規模個人再生はできないことになります。
これは、読んで字のごとく、半分以上の債権者が反対した場合です。
例えば、債権者が7社あったとしましょう。
この場合、4社以上が個人再生に反対すると、小規模個人再生はできないということです。
これは少し複雑なのですが、借金額の1/2を超える額の債権者が集まった場合ということです。
例を出してみましょう。
・A社:200万円
・B社:150万円
・C社:100万円
・D社:100万円
・E社:50万円
この場合、借金合計は600万円です。
借金額の1/2は300万円ですので、個人再生を反対する債権者の額が300万円を超えると小規模個人再生ができなくなります。
例えば、A社とB社が反対した場合は借金額が350万円なので、300万円を超えていますので、債権者の主張が認められてしまうというわけです。
偏波弁済とは、特定の債権者に優先して返済してしまうことです。
よくある例は、カード会社の返済をせずに、親や知人のような身内の借金を優先的に返済してしまうことです。
個人再生では、債権者平等の原則が絶対的なものとして存在します。
これは、全ての債権者を平等に扱わなければいけないということであり、各債権者に不平等が生じることを防ぐためのルールなのです。
もし、 偏頗弁済していることを裁判所が知ることとなれば、個人再生は認められなくなってしまいます。
個人再生ができず失敗に終わると、もう借金問題を解決できないのかというと、そういうわけではありません。
個人再生を申し立てる前に、事前に司法書士が認可されそうかどうかを判断し、司法書士が認可されるだろうと判断できた場合は殆どのケースで失敗することは無いと考えて良いでしょう。
※個人再生の経験があまり無い司法書士であれば判断を誤る可能性はあります。
個人再生ができない場合は、「債権者の不同意」が原因となるケースが多いのですが、その際は、もう片方の個人再生、給与所得者再生で再申請をしていきます。
給与所得者再生は、債権者の同意を得る必要は無いため、小規模個人再生ができない原因となっていた「債権者の不同意」を払拭できるわけです。※給与所得者再生の方が減額幅が小さくなる傾向があります。
また、再生計画案が不適切で裁判所から不認可とされる可能性もありますが、その場合も再生計画案を練り直し再申請をすることで認可してもえる可能性が高まります。
個人再生は、再生計画案通り返済してく為の能力が求められます。
言い換えると、申立者本人に継続した安定的な収入が求められるわけですが、それに満たない場合は任整理を検討してみましょう。
任意整理は、司法書士と債権者が直接交渉することで返済していきやいように調整する方法です。
そして、任意整理では必ずしも自分自身に返済能力が無くても問題無いのです。
例えば、任意整理後の返済をご両親や配偶者がしていけるのであれば、それでも任意整理は進められるのです。
個人再生のように元本の減額効果は認められませんが、将来利息のカットはできるため、現状より良くなることは間違いないでしょう。
個人再生に必要な返済能力が無く、さらには両親や配偶者など頼れる人がいない場合は、自己破産を検討せざる得ないでしょう。
自己破産であれば、借金がゼロになるため全く返済能力が無くても認められます。
また、個人再生では、5000万円を超える借金は手続きできませんが、自己破産に借金額の制限はありませんので、借金額が5000万円を超える方は自己破産を検討してみましょう。
個人再生ができないケースは大きく分けて7つあります。
① 返済能力が無い
②100万円未満もしくは5000万円以上の借金
③清算価値が借金額を上回っている
④司法書士費用・裁判費用が工面できない
⑤住宅ローンに他の担保権が設定されている(住宅ローン特則を利用する場合に限る)
⑥債権者による不同意(小規模個人再生の場合に限る)
⑦ 偏頗弁済をしてしまった
これらいずれかに該当する場合は個人再生ができない可能性が非常に高くなってしまいます。
ただし、必ずしも個人再生ができないわけではないので、まずは司法書士に相談してみましょう。

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら