債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。

札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
|---|---|
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
債務整理なら札幌市のみどり法務事務所の司法書士にお任せください。

札幌市で債務整理を司法書士に無料相談なら
札幌債務整理相談室
<運営:みどり法務事務所>
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
※JR札幌駅徒歩1分
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
|---|---|
| 休業日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ営業時間外でも対応可能です。 |
対応手続き
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求
札幌債務整理相談室HOME > 債務整理とは > 債務整理による保証人への影響
更新日:2025/05/19

債務整理 をする場合、保証人への影響があるのではないかと心配で、二の足を踏んでいる人も少なくないでしょう。
そして実際のところ、あなたが債務整理することによって、保証人へ悪影響がある可能性があります。
その場合、保証人への悪影響を回避する方法はないのでしょうか。
今回は、債務整理による保証人への影響について詳しく解説していきます。
目次
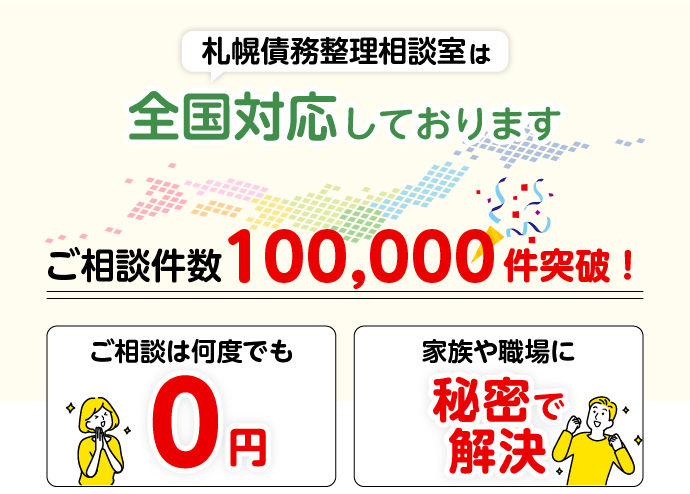
保証人とは、借金をした本人が返済できなくなった場合に、そのかわりに借金の返済の責任を負うことになる人です。
債務整理では、借金の利息を無くしたり、元本を減らしたり、ゼロにするなど、債権者との契約内容を変更することとなります。
主契約者が債務整理により契約通り返済できないとなると、 保証人がかわりに返済責任を負うことになり、多大な悪影響を与えてしまうようになります。
債務整理の最大のネックのひとつでもあり、手続きに踏み切れない人も少なくありませんが、全ての債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)が必ずしも保証人に影響を与えるわけでもありません。
まず基本的な事として、
①通常保証
②連帯保証
...の区別があります。
もっとも一般的には借り入れ 契約をすると、「連帯保証人」を要求されます。
連帯保証人は、通常保証よりも責任が重いのが特徴で、 債権者とほぼ同等の責任があると考えてよいでしょう。
なので、いきなりカード会社から一括返済を求められ、有効な対策を講じることもできず、窮地に陥るようなこともありえます。
保証人については、借金をしている人がどうしても返済不可になった場合にのみ、返済義務が生じる保証です。
連帯保証人には通常、保証人が持つ次のような3つの権利が認められていません。
・「催告の抗弁権」
・「検索の抗弁権」
・「分別の利益」
これらの権利が認められない理由は、連帯保証契約の特性によるもので、連帯保証人は主債務者と同等の責任を負うためです。
そのため、連帯保証人は自らの権利を主張しにくく、責任を追及される方法も保証人とは異なります。
これら3つの権利の違いを踏まえ、連帯保証のリスクと責任の重さを解説していきます。
保証人は、主たる債務者が借金の支払を履行しない場合に、債権者から請求を受けます。
この際、保証人には「催告の抗弁権」という権利が認められています。これは、保証人がまず主債務者に対して支払いを請求するよう債権者に催告を求めることができる権利です。ただし、この権利が行使できるのは、主債務者が破産しておらず、行方が明らかな場合に限られます。
一方、連帯保証人はこの催告の抗弁権を持たず、債権者は主債務者に請求することなく直接連帯保証人に債務の履行を求めることが可能です。このため連帯保証人は、債務者の状況にかかわらず速やかに借金の支払義務を負うこととなります。
債務者の破産や行方不明といった事情がない限り、保証人はまず主債務者に請求を優先させる権利を主張できますが、連帯保証人はこの権利を行使できない点が異なります。
検索の抗弁権は、保証人が借主の代わりに返済の請求を受けた際、まず借主に返済を求めることや借主の財産を差し押さえるよう主張できる権利を指します。
これは保証人によって借主の財産を優先的に活用してもらうための守るべき権利です。
しかし、この権利は連帯保証人には認められていません。連帯保証人の場合、債権者から直接請求がきたら検索の抗弁を主張することなく、すぐに返済対応をしなければならないのです。
分別の利益は複数の保証人がいる場合に適用され、各保証人の債務負担を保証人の頭数で按分する権利です。
これにより、保証人一人ひとりの返済義務は借金の全額ではなく、分割された範囲内に限定されます。
しかし、この利益は連帯保証人には認められません。連帯保証人は借金の全額に対する返済義務を負い、分別の利益が通用しないため、その責任は保証人よりも重くなります。
保証人と連帯保証人の違いやこの利益の扱いは、保証や債務整理に関する重要なポイントの一つであり、権利と義務を理解するうえで不可欠です。
「連帯保証人だけは、絶対になっちゃいかん!」と親から言われたことがある人も、納得できる違いを理解できたのではないでしょうか。
債務整理をするにあたり、もっとも気がかりになることの一つが、連帯保証人ではないでしょうか。
債務整理では連帯保証人に、少なからず迷惑をかけることになります。
下記では、債務整理が保証人に及ぼす影響について解説いたします。
任意整理すると基本的に保証人にも悪影響があります。
任意整理を行うと、本来借金をした本人が返済すべき金額の返済義務が保証人に移ります。
つまり、保証人付き借金を任意整理しようとすると、条件変更の和解交渉ができず、単純に保証人に請求が行ってしまうというわけです。
しかし、任意整理には、整理する対象を自由に選択できるという特徴があります。
例えば、
このような借り入れ状況だった場合、B社とC社だけを任意整理し、A社を任意整理の対象から外すことで保証人への影響を回避することができます。
保証人付き借金がある方は、任意整理を検討してみるとよいでしょう。
個人再生と自己破産の場合は、保証人へ影響を及ぼしてしまいます。
なぜなら、個人再生と自己破産については、任意整理のように整理対象を自由に選べないからです。
個人再生と自己破産では、 債権者平等の原則が厳守されることになり、全ての借金が強制的に整理対象になります。
自己破産の場合、全額が保証人に請求がいき、個人再生の場合は、不足分(500万円が100万円に減額出来た時は400万円)が請求がいくことになります。
保証人は一括返済を求められ、分割払いが認定されるケースもあるのですが(これは債権者との交渉次第となります)、 それでも返済が難しいのであれば、保証人も債務整理しなければならない状況に陥ってしまいます。
個人再生の手続きにおいては、主債務者と保証人は両者が分割して債務の返済を進めることが求められます。
ただし、保証人が主債務者の返済計画に対して過剰に支払った場合、その負担は著しく大きくなります。こうした状況では、保証人は主債務者に対して自己が支払った分の返還を求める権利を有しています。
そのため、主債務者は保証人から請求を受けるようなケースに発展する可能性があります。
返済の開始時から、返済額や支払いのペースに注意を払い、保証人の過度な資金負担がないように調整することが重要です。債務者と保証人のバランスを考慮しながら、債務全体の支払管理を行う必要があります。
自己破産した場合は、債務者本人の借金は免責されますが、保証人や連帯保証人の債務は残る点に注意しましょう。
これは民法に基づく制度で、保証人は主債務者の支払不能時に債権者に代わり負担を負う役割を持つためです。
特に、連帯保証人は、3つの抗弁権が認められず債権者から直接請求を受けるリスクが高くなります。
自己破産で本人が免責されても、保証人の支払義務は継続し、債務整理のメリットとは別に重い負担が残るのです。
債務整理をすると保証人もブラックリストになるのではと心配に思っている人も少なくないようですので、詳しく説明していきましょう。
各カード会社の取引情報を管理する「信用情報機関」と呼ばれる会社により、借金の返済ができなかった場合の「事故情報」がデータベースに登録され、以後5~7年程はローンやクレジットカードの作成、キャッシングなどはできなくなります。
このことを、一般的に「 ブラックリストに載る 」といいます。
借入契約に保証人がつけられた場合、その保証人はカード会社にとって「回収不能な状況になった時の切り札」なので、審査対象となります。
ただ、このタイミングではまだ、「保証人になった」というデータが記録されるだけです。
借金をしている人が通常通り返済しているのであれば、問題はありません。
もし借金をした本人が、借金の返済が困難になって滞納したり債務整理をしても、その時点で保証人がブラックリストになるわけではありません。
保証人が代わりにしっかりと返済していけるのであれば、保証人がブラックリストになることはないのです。
しかし、保証人が返済できない場合は、事情が異なります。
保証人に移った借金の返済を滞納したり、返済が難しく債務整理をすることになると保証人もブラックリストになってしまうというわけです。
もちろんブラックリストに載ってしまうと、未成年者がローン契約を行う際に大きなリスクが伴います。
未成年の場合、本人の信用力不足を補うために親や第三者の保証人を必要とすることが多く、債務整理や自己破産といった借金問題が生じると保証人に負担が及ぶ可能性が高いからです。
上述したように、保証人になること自体は未成年者のローン契約に影響を及ぼしませんが、保証人として債務整理を行なったケースでは、信用情報に影響が出るため子どものローン契約などが円滑に進まなくなります。
ブラックリストについて詳しくはこちら
任意整理をした過去があっても、保証人になれるケースは存在します。
特に、奨学金の保証人や賃貸契約の保証人の場合は、信用情報機関に事故情報が記録されていたとしても、必ずしも制限されるわけでないからです。
任意整理後、5年間は信用情報に履歴が残りますが、この記録が保証人になる資格へ直接影響を与えるかは、契約内容や金融機関の判断次第で異なります。
整理後の借金状況や過去の事故の有無を踏まえ、必要な対処を行うことで、問題なく契約が可能となるケースも多くあります。
したがって、任意整理をしていても保証人になれる可能性は十分にあります。
奨学金は、連帯保証人を必要としない場合も多くあります。特に日本学生支援機構の制度では親などの保証人が不要となる機関保証制度が実施されています。
具体的には、一定の保証料を支払うことで公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)が元金や利息の支払いを保証してくれるため、保証人を立てずに奨学金の借り入れが可能というわけです。
過去に任意整理をした場合でも利用できるケースがあり、本人が自らの責任で申し込む制度です。
返還が遅延した際は法人が一時的に支払いますが、その後本人に全額請求されるため、返還計画の把握と支払い義務の理解が重要となります。
賃貸契約において、従来は保証人が必要とされてきましたが、近年では保証会社の利用が一般的となり、保証人が必ずしも必要ではありません。保証会社を利用することで、家主と借主双方の信用情報の確認が可能となり、よりスムーズな契約が実現します。
また、金融機関と異なり、不動産会社ではそもそも信用情報を細く確認できないからです。子どもが独立して自宅を離れる際も、保証人の過去の債務整理や金融状況が直接契約に影響しにくくなっています。
こうした環境変化により、賃貸契約は保証人なしでも成立しやすく、保証会社が提供する保証が契約の安全性を高め、債務リスクの整理にも役立っています。
自身の信用状況に不安があっても、保証会社を利用することで賃貸契約が円滑に進むことが多くなっています。
債務整理による賃貸契約への影響
配偶者が債務整理の保証人や連帯保証人になっている場合、借金の返済義務は家族全体に影響を及ぼすリスクがあります。
債務整理の方法によっては、主債務者が返済不能になった際に保証人である配偶者に借金の返済責任が移ることがあるため、家族の生活にも大きな負担がかかる可能性に注意しましょう。
特に連帯保証人の場合、返済の責任は主債務者と同等となり、債権者から直接返済を求められるため、手続き後も負担が免除されるとは限りません。子どもの将来にも影響を及ぼす恐れがあり、慎重な対応が不可欠です。
債務整理の手続きでは、家族を守るためにどのような解決策があるのかを把握し、適切な方法を選ぶことが重要です。専門家の助言を受けながら進めることで、リスクの軽減が期待できます。
とはいえ、任意整理や個人再生などの債務整理では、借金の減額や返済計画の見直しが行われますが、保証人でない限りたとえ家族であっても債務の返済義務を負う理由はありません。
任意整理の手続きにおいては、個人が債務整理する対象を選べるため、保証人がついていない借金だけを対象とすることも可能です。
こうした仕組みは、保証人と債務者の法的な区別に基づくもので、保証人でない限り借金の返済義務は発生しないため、不必要な返済負担を負うことはありません。
保証人は、たとえ離婚しても借金の返済義務から免れることはできません。
保証契約は婚姻関係の有無によらず、有効に続くため、離婚後も保証人としての責任が継続するからです。
したがって、元配偶者が返済できなくなった場合、保証人は引き続き債務の返済義務を負い、これに伴う返済記録も信用情報機関に残るリスクがあります。
保証人には法的な返済義務が生じるため、離婚後の経済的な負担に注意が必要です。
相続においては、被相続人の債務も財産とともに自動的に引き継がれます。そのため、相続人は借金などの債務も負う必要が生じる点に注意が必要です。
相続の際には、相続財産と債務のバランスをよく検討することが重要です。
債務が財産を上回る場合は、相続放棄を検討すべきですが、放棄すると財産も一切受け取れなくなります。
したがって、本人や家族が状況を正確に把握し、法的対応を慎重に判断することが求められます。
信用情報機関では、債務者本人の債務状況や事故情報が登録され、カード会社はこれを基に審査や管理を行います。
配偶者の信用情報に問題ない場合でも、カード会社が申込者の名前や住所から情報を照会し、債務の事故が確認されると、その影響が配偶者のカード利用に及ぶ可能性があります。
たとえば、配偶者の信用情報がカード会社により参照され、本人の債務状況が信用リスクとして認識されると、カードの限度額の引き下げや発行の拒否など、利用制限がかかる場合があります。
したがって、個人の信用情報管理は本人だけでなく、配偶者のカード利用にも一定の影響を与え得ることを理解しておきましょう。
債務整理を行う時点で子どもがいる場合には、その後の人生に影響を及ぼす可能性があります。
特に、進学や就職などの重要な局面で、家計の状況が制限されるのではと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
債務整理により家計の負担は軽減されますが、支出の見直しや信用情報の変化が長期にわたって続くこともあるため、どのようなリスクがあるかを事前に押さえておきましょう。
大前提、保証人ではない限り、子どもが借金の返済義務を負うことはありません。
債権者や貸金業者が、債務者の子どもであるという理由だけで返済を要求しても、その主張は認められません。返済の必要があるのは、契約上保証人として名簿に記載されている者に限られるからです。
子どもや家族であっても、保証人の同意なく債務の肩代わりを求められることはなく、仮に求められたとしても拒否できます。債務者本人が返済できない場合でも、保証契約がない限り他人に返済義務は移りません。
したがって、返済の代わりを要求される理由は成立しません。これは法的にもしっかり守られている権利ですのでご安心を。
親が債務整理を行っても、子どもの進学や就職に及ぼす影響は極めて少ないです。
学校や進学先が保護者の債務の有無を知ることはほぼなく、進学の選択や資格取得の自由は妨げられません。
就職についても、国家資格の取得や職業選択は債務整理の有無に関係なく自由に行えます。
したがって、債務整理の影響が子どもの将来に直接及ぶことは基本的にありません。安心して債務整理を検討できます。
債務整理をしたことは戸籍などの書類に記録されないため、結婚に直接的な影響は基本的にありません。
事実、債務整理をしても、その情報が家族や子どもの人生に直接伝わることは少ないのが現状です。そのため、債務整理によって子どもが結婚で不利益を被る心配はほとんどないため、債務整理を通じて新たな生活の再スタートを切ることが可能です。
ただし、債務整理したことを口外するなど、結婚相手の親族などに知れ渡ると、悪い印象を持たれる可能性は否定できません。そのため、債務整理したこと自体の情報管理には気をつけるようにしてくださいね。
奨学金を利用する際には、連帯保証人や保証会社の利用について注意が必要です。
奨学金によっては、連帯保証人が必要となることがあるため、その際は家族が保証人となることが一般的だからです。
しかし、保証人の信用情報に事故情報が登録されている場合は、保証人として認められないことがあります。こうしたケースでは、保証料を支払って保証会社を利用する方法を検討しましょう。
保証会社の利用は連帯保証ではないため、家族のリスク軽減につながります。信用情報機関への情報登録も関係するため、利用する際は保証条件をよく確認し、連帯保証人の負担やリスクを理解したうえで進学の計画を立てることが重要です。
奨学金の債務整理について
債務整理の手続きを検討している場合は、各手続きのメリットとデメリットを十分に把握して、借入契約に連帯保証人がついている場合、お互いにとって、もっとも被害が少ないやり方は何かということを、慎重に判断しなければなりません。
また、債務整理をする前には、配偶者や家族への影響もしっかり考えたうえで検討しましょう。短期的なメリットが得られても、長期的に後悔するケースは少なくないからです。
いずれにせよ、まずは司法書士へ相談することをお勧めいたします。
・任意整理であれば、保証人の付いている借金を除外して、債務整理することができるので、迷惑をかけずに行える可能性が高い
・個人再生や自己破産は、保証人に請求が行く等、保証人に悪影響がある
・保証人には『保証人』と『連帯保証人』の2種類があり、そのうち連帯保証人には以下の権利がないため、保証人以上に重い責任がのしかかる点に注意が必要。
①催告の抗弁権
②検索の抗弁権
③分別の利益

監修者:みどり法務事務所 札幌駅前事務所
代表司法書士鈴木 健太
札幌司法書士会所属
会員番号 第823号|認定番号 第843020号
借金のお悩みはなかなか一人では解決できるものではありません。そのために私たちがいます。皆様のお話をお伺いし、できる限りのお手伝いをいたします。
> 司法書士紹介はこちら